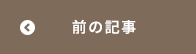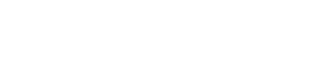口内炎の対処と予防

こんにちは(こんばんは)、歯科医師の嶋本です。
「口内炎」とは、口の中や周辺の粘膜に起こる炎症の総称です。口内炎の多くは、頬の内側や舌、唇やその裏側といった柔らかい部分にできます。そのほかにも、のどや口蓋垂、歯茎、上あごの裏側など、粘膜であればどこにでもできる可能性があります。1週間から2週間で自然に治癒しますが、痛みや不快感を伴うことがあります。
原因は?
①口の中の傷
口の中に生じた傷に細菌が繁殖すると炎症が起こり、口内炎ができます。
②新陳代謝の低下
栄養不足、ストレス、疲労などが原因で新陳代謝が低下して口の中に潰瘍が生じ、そこに細菌が繁殖して炎症を起こして、口内炎ができます。特に粘膜を守るビタミンB群の不足により粘膜が薄くなり傷がつきやすくなっていたり、栄養不足により抵抗力が低下していると炎症を起しやすくなります。
③唾液の減少
唾液が減少すると修復機能が低下して口内炎ができやすいと言われています。唾液は、口腔内の汚れを洗い流して抗菌の働きをしてくれます。また、粘膜の保護や修復を行う役目もあり、口腔内を正常に保つためにとても重要なのです。つまり、歯磨きや食事、頬を噛んだりして口の中に傷ができた場合、唾液の分泌が少ないと細菌を洗い流せずに増殖して口内炎ができてしまいます。
対処法は?
・自然治癒
口内炎は通常、1~2週間で自然に治癒します。治癒を促すためには、口腔内の衛生状態に注意し、刺激の少ない食事をすることが重要です。
・マウスウォッシュやうがい薬の使用
抗菌作用のあるマウスウォッシュやうがい薬を使用することで清潔を保ち、感染を予防することができます。
・栄養と水分摂取
栄養バランスの良い食事を摂取し、ビタミンやミネラルの補給を心掛けましょう。口内炎の治療や予防にはビタミンB2、ビタミンB6が有効です。また、半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)などの漢方薬も効果があるとされています。
口内炎に効くビタミンB2とビタミンB6
ビタミンB群であるビタミンB2は、肌と脂質の代謝を助け、肌細胞の再生や成長を促進し、ビタミンB6は、粘膜を保護し、細胞の再生を助けてくれます。口内炎を緩和するために必要なビタミンB2やビタミンB6は、水溶性ビタミンで尿から排出され体内に蓄積しにくいため、こまめに摂取するしかありません。
ビタミンB2は牛・豚・鶏のレバー、海藻、サバなどの青魚、ウナギ、納豆、トウガラシ、卵、乳製品などに多く含まれており、ビタミンB6はニンニク、バナナ、鶏のササミ、牛・豚・鶏のレバー、マグロ、カツオ、トウガラシなどに多く含まれています。
またビタミンCは、免疫力アップが期待でき、口内炎を早く治す効果があります。 ビタミンCも水溶性で2〜3時間ほどで体外に排出されるため、こまめに摂取するのが効果的です。アセロラ、グァバ、ピーマン、芽キャベツ、ブロッコリー、キウイフルーツ、いちご、じゃがいも、さつまいもなどに多く含まれています。ビタミンCは水に流れやすいため、調理のために野菜を水洗いする際はなるべく短時間で行いましょう。
食べやすいもの
おすすめの食べ物は、食感が滑らかで柔らかいもの、熱すぎないもの、スムージーやヨーグルトなどの流動食などです。また水分をとって口の中を湿らせておいたり、ストローを使って患部を避けるようにすると、刺激を与えずに食事を摂ることができるでしょう。例)プリンやゼリー、ヨーグルト、おかゆ、柔らかめに炊いた白米、煮物、スムージー、野菜ジュース
ヨーグルトをはじめとする乳製品は、ビタミンB2が豊富で、滑らかで刺激も弱いため、口内炎を早く治したい時に効果的です。
避けたほうがいいもの
辛いものや熱いもの、味の濃い食べ物は避けるようにしましょう。アルコール類や糖質の多い食べ物も注意が必要です。
- 辛いもの
熱いスープや麺類なども口内炎を刺激し、悪化させる恐れがありますので、少し冷ましてから食べましょう。
- 味の濃いもの
ソースのかかったお好み焼き、焼きそばなど味の濃いものには塩分や香辛料が含まれているので口内炎に刺激を与えます。
- 甘いもの
ケーキやお菓子など砂糖を多く含んだ食べ物は、分解する時にビタミンB群を消費してしまいます。
- アルコール類・炭酸飲料
アルコール類も分解する際に大量のビタミンを消費します。ビールなどの炭酸系アルコール飲料は、炭酸の刺激が口内炎を悪化させる可能性があるのでさらに注意が必要です。
- 酸っぱいもの
柑橘類、漬物などの酸っぱいものはなるべく避けたほうが痛みが生じにくいです。
- 糖質の多い食べ物
ごはん、パン、ラーメン、パスタ、うどんなどの糖質は、体内で分解する際に多くのビタミンを消費するので、栄養バランスを考えて食べるようにしましょう。
最後に
ストレスを溜め込むと、体内の血流や代謝が滞りがちになります。その結果、口内の粘膜の再生機能が低下し、炎症を起こして口内炎ができやすくなります。ストレスが続いて粘膜の再生機能が低下したままだと、口内炎を繰り返したり、長引かせることになるでしょう。しっかりと睡眠をとってストレスを軽減し、免疫力を回復させましょう。